平成27年6月7日、気持ちの良い晴れ空が広がり気持ちのいい風が吹く(ちょっと冷たいけれど)野付半島で、別海町ボランティア研修会が開催されました。
野付半島の雑草除去は21回目となります。ラムサール条約に湿地登録されている野付半島は別海町にとって大切な自然環境であるとともに観光資源としても欠かすことができません。
別海町ボランティア連絡協議会の主催で、各ボランティア組織の方に加えて、チラシを見た一般町民の方や、根室振興局の職員の方など150名近くの参加者がありました。
例年であれば在来種であるシコタンタンポポを保護するために、外来種のセイヨウタンポポを抜く作業や海岸の清掃作業などが中心となるのですが、昨年12月の高潮により大量の藻が半島内に入り込んでしまっており、この藻の除去が今回の優先内容です。
その「藻」は、甘藻(アマモ)というもので、別名「リュウグウノオトヒメノモトユイノキリハズシ(龍宮の乙姫の元結の切り外し)」と言われ、最も長い植物名として知られています。
このアマモ、実は胞子で増える藻ではなく海中に生える種子植物で、イネ科に近い特徴を持っているそうです。水質や砂泥質の底質が清浄であり、自然の海岸線や海底が残っていないと生育しないため、海岸の指標生物ともされています。
また、アマモは遠浅の海底にアマモ場と呼ばれる大群生を作り、これが潮流を和らげたり外敵からの隠れ場となるため、稚魚や小型動物のかっこうの生息場所となっています。
と、アマモ自体はとってもいいヤツで、むしろこんなに大量にあるのは誇らしいことですらあるのですが・・・この様に陸に揚がってしまうと中々やっかいなことになります。
この様にハマナスの群生地にところどころアマモが大量に積もってしまっているのです。厚いところでは30cm程度も積もってしまい、完全にハマナスが埋もれてしまっています。細長いアマモの枯れたものは複雑に絡み合い、まるで織り込まれた分厚い布のようになっており(しかも下は湿ってる!)剥がすのも一筋縄ではいきません。
そうして分厚いアマモを剥がしていくと、下から折れ曲がったハマナスが出てくるので絡まったアマモを丁寧に除去していきます。写真にも小さく写っていますが、ハマナスの新芽はアマモの下でも伸び始めていました。太陽の光が当たらないのでホワイトハマナスですが(笑)アマモに埋もれていないところは花の蕾ができ始めている頃なので少し生育は遅いですが、なんとかきれいな花を咲かせて欲しいところです。
アマモを掘り起こす作業に没頭していると・・・あっという間にとんでもない量のアマモの山ができあがってしまいます。これをフレコンバッグやゴミ袋に詰めていきます。下の方は湿って水を大量に含んでいるので中々の重量になります。
集めたアマモの運搬は「手」です!車が自由に走れる道は整備されていないので仕方がありません。後半なんとか軽トラが入れるようになったのですがピストン輸送が間に合わずに手運びも続行。かなり強烈なトレーニングになります(笑)
ネイチャーセンターまで運んだら清掃のプロ集団「渡邊清掃(イベント協力)」がトラックに積み込んでくれます。今回はこのトラックいっぱいになったところで作業終了となりました。
アマモの堆積したエリアは各地に点在しているようで、遊歩道からの景観がよろしくないなどの問題もありますが、なにより植生への影響が出ないタイミングで除去作業をしていかなければなりませんね。
高潮もアマモも自然環境の中で起きたことなので、必ずしもアマモの堆積による植生への影響が「悪い」わけではありません。しかし、人間がその自然を楽しむために特定の環境を保全することは意義のあることだと思います。手間もかかることなので、できる限りで努力するしかありませんが頑張っていきましょう。
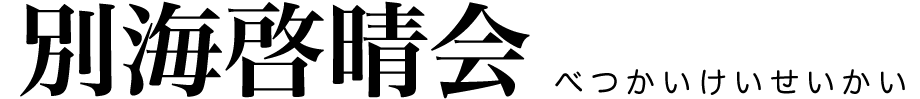











LEAVE A REPLY